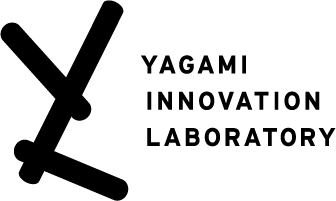オープン目前! 学生主催のプレイベント
「YIL Open Talk〜立場を超えて、慶應の未来を語ろう〜」

2025年4月、慶應義塾大学矢上キャンパスに誕生する「YIL(Yagami Innovation Laboratory)」。 そのオープンを目前に控えた3月26日、34棟・コラボレーティブデザインルームでプレイベント「YIL Open Talk〜立場を超えて、慶應の未来を語ろう〜」が開催されました。イベントを主催したのは、理工学部の1・2年生を中心とする「YIL プレイベント学生有志」のメンバー。理工学部内外の学生や教職員など約30名が参加しました。
冒頭ではYILの設計・運営に関わる教員や建設会社の方々を中心にしたパネルトークが行われました。
斎木敏治教授はYILについて、1階が“集う場”、2階は“試す場”として、対話と実践が同時に生まれる空間にしたいと語りました。YILには狭いからこその良さがあるとしつつ、「みんな対等、肩肘張らずに。YILから文化を。」と学生へ想いを伝えました。

斎木敏治教授
牛場潤一教授は、分野を超えた交流によって、学生に新たな関心や強みを見つけてほしいと語りました。加えて、「YILにはさまざまな仕掛けを用意しているので、楽しみながら発見していってほしい」と前向きなメッセージを添えました。

牛場潤一教授
美術史を専門とする荒木准教授は、アートの要素も加わり、人と人とのつながりが自然に生まれるような空間になってほしいと語りました。また、自身が主催する「女子会」を引き合いに出しながら、専門性にとらわれず、個人の関心や日常的な感覚も気軽に持ち寄れるような、開かれた雰囲気をYILに期待していると述べました。

荒木文果准教授
設計を手がけた(株)安藤・間の弓野さん・上野さんからは、YILの空間に込めた工夫と想いが紹介されました。細部に違和感がないよう設計することこそが成功だと語るお二人。さまざまな用途を持つYILで、学生一人ひとりが好きな場所を見つけてほしいと語りました。

(株)安藤・間 弓野将義さん

(株)安藤・間 上野桃さん
続くグループディスカッションでは、登壇者と参加者が5〜6人のチームに分かれ、「YILで自分が挑戦したいこと」をテーマに自由にアイデアを出し合いました。
「こんなの無理じゃないかと思うような意見も出してみてください!」という司会の学生の言葉をきっかけに、アイデアは一気に広がっていきました。

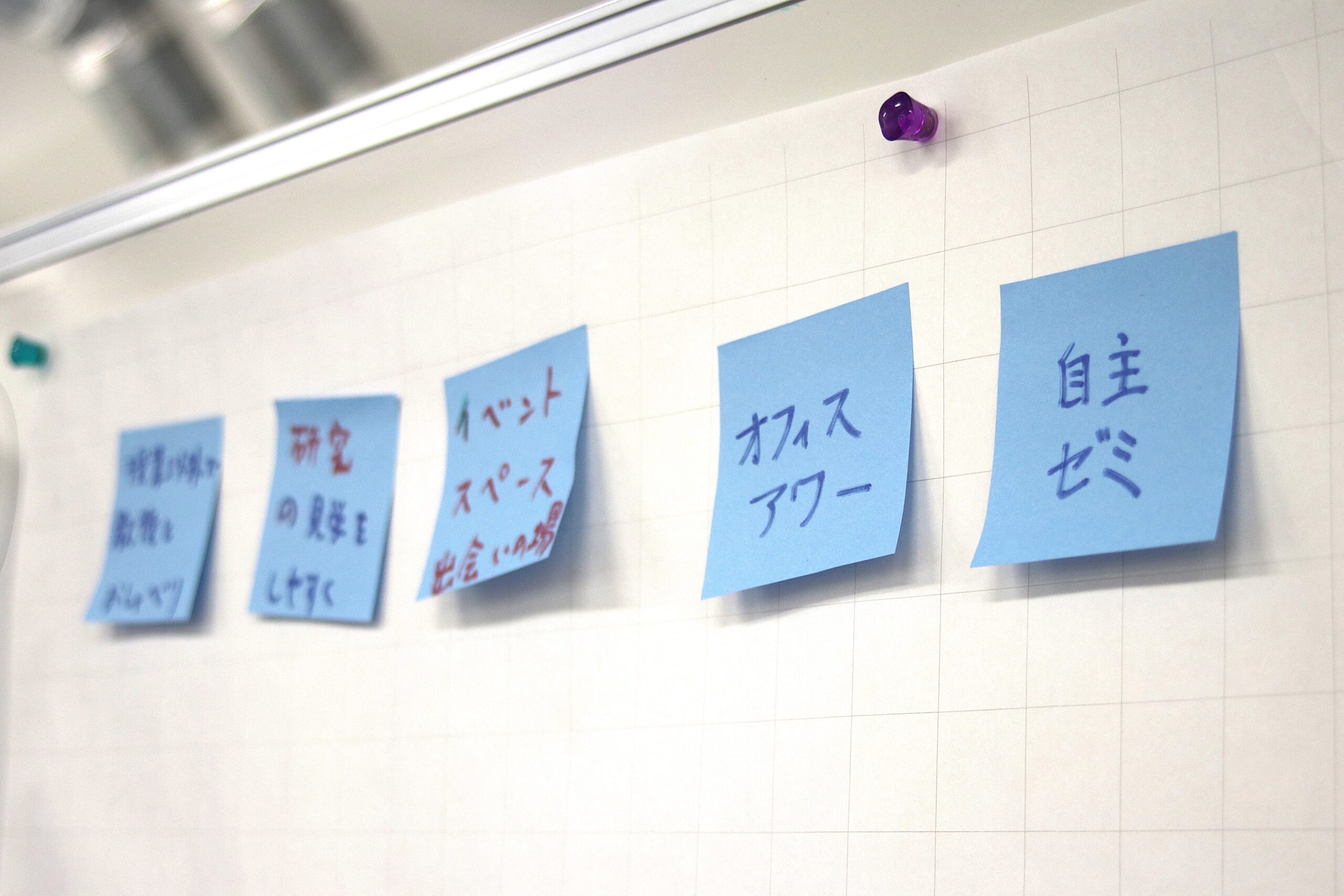
トークセッション第2部では「ヒューマンAIインタラクション」をテーマに、ヒューマンインタフェース、言語学、科学社会論といった分野の専門家たちと学生によるパネルディスカッションが行われました。
まず学生から、技術の進歩がもたらすAIと人間との新たな関係性について問いが投げかけられました。議論は次第に、研究や教育現場におけるAIの役割、AIと人間の意思決定の境界、さらには日常的なコミュニケーションにおける違和感や可能性といったテーマへと広がり、AIと共に生きる社会のあり方を多角的に考える時間となりました。

杉本麻樹教授

杉山由希子准教授
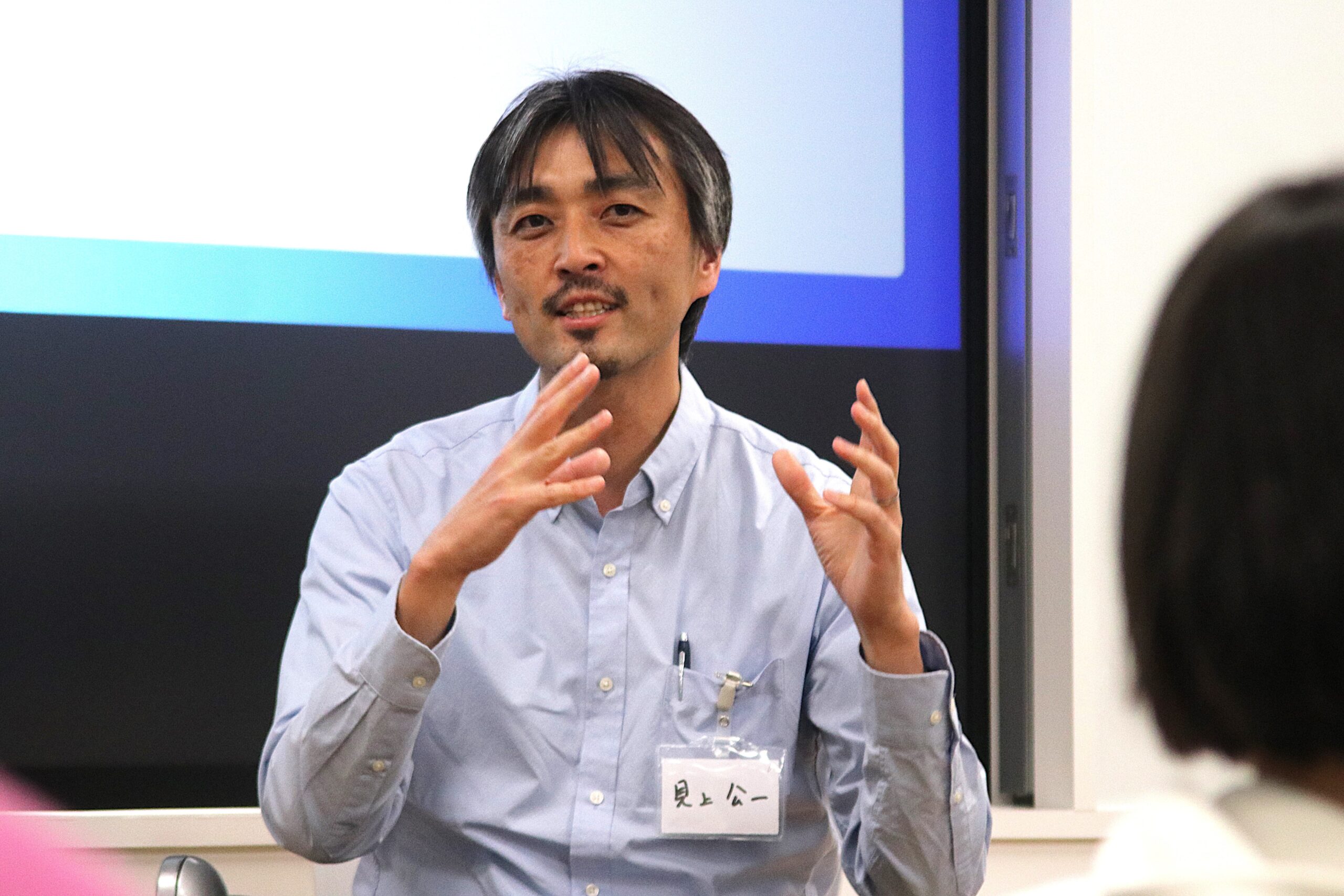
見上公一准教授
その後、「あなたにとってのAIとの関わり方」をテーマに、再びグループディスカッションが行われました。各グループは話し合いを通じてキーワードを3つに絞り込み、それをフォームに入力。AIがそれぞれの言葉の意味を数値的に捉え、ベクトル空間上で可視化しました。画面上に浮かび上がった3Dマップには、異なるグループの視点や関心の違いが視覚的に表れ、思考の距離や共通点を直感的に読み取ることができました。

イベント後には学生ラウンジでの立食懇親会へ。 学生・教職員・登壇者が自由に語り合うなかで、これからYILが生み出されるさまざまな出会いやきっかけに、さらに期待が膨らみました。
編集手記
短いイベントでしたが、参加者それぞれの思いやアイデアに触れることができる濃密な時間となりました。ディスカッションでは自分の発言を誰かに受け止めてもらえることで、新たなアイデアが次々に生まれていくのを感じました。4月から始まるYILも、一人ひとりが自由に表現できる場であると同時に、その表現同士が出会い、新たな化学反応が起きる場になってほしいと感じます。まだ真っさらなキャンバスであるYIL。これから、僕たちの手で“YILから文化を”作っていけたらと思います。(理工学部2年 鏡理吾)